
「屁放き爺さん昔~しのお噺」
伊勢遙拝ー天照大女神の誕生ー
巻四の3
二寺には明日香の都に聳え立つ川原寺と同じ紋様の瓦の使用が許された。或いは、川原寺を建設した渡来人が建造したとも考えられる。何れにせよ、壬申の乱勝利の大きさと、海部族の助力が天武持統朝の誕生に大きな貢献をしたと言える。今、二つの寺は廃されて遺跡として、住宅地に名を残すだけである。
斯くして聖徳太子に始まり、大化の改新、壬申の乱、天武朝の成立という動乱の時代は終わり、日本は中央集権国家を樹立して唐から文化を積極的に受け入れ、”咲く花の匂うが如き”平和な時代を迎えるのである。
因みに此の後、天武天皇の崩御をうけて即位した鸕野讃良つまり、持統天皇は皇位を孫の軽皇子(文武天皇)に譲った。息子草壁皇子の死によって自らの血統を守る為で在った。此の後更に、早世した文武天皇の後を受けて草壁皇子の妃、元明女帝が即位、文武天皇の后元正女帝を経て孫の首皇子(聖武天皇)に皇位は受け継がれる。都も明日香から藤原京、平城京へと大都城が建設される。
梅原猛先生は”此の持統、元明両女帝の孫への皇位譲り渡し劇が、’天照大女神が日本という国を孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に譲った’という古事記天孫降臨神話に語られる神話が、文武聖武二代の皇位継承劇を正当化する物語で在る”と述べられる。筆者も此の梅原説は、一考に値する注目点で在る??と思う。
此の首皇子つまり、聖武天皇と其の娘、孝謙女帝によって日本で一番の平和な時代で在ったと云われる天平の時代が到来し、青丹よし 平城の都は 咲く花の・・・と詠われる平城京の誕生と為るので在る。

”斯くして聖徳太子の夢は完成した”
天武天皇は即位と同時に、大来皇女を齋宮に任じて伊勢神宮を祀らせる。彼女は13年間を伊勢の国に留まる。此の後も齋宮制度は続いて天皇家と伊勢神宮の結び付きの強さは現代に至っている。此は壬申の乱に海人族が大きな役割を果たした事を物語る証拠とも云えない事はない。伊勢の大神は海の安全を護る、海の豊穣を祈る神で海人族が祀る神として伊勢湾の出口に鎮座した神で在ったと想像する。
天武持統両帝の天下取りの戦いに協力した海人族の長と逃亡路を確保した伊賀の豪族には功労として寺を建てる許可が与えられた。桑名の額田廃寺と名張の夏目廃寺である。当時、寺を建てるという事は大事業で当然、渡来人の技術が要った。海部族の地には彼等は居ず、都から呼ばれた。また、寺の瓦の紋様は大きな意味を持つ。聖武天皇勅願の東大寺には平城京に使われていた瓦が敷かれ、平城の大寺院にはそれぞれ寺の格式が瓦の紋様に表されているという。
海部族に対する天武持統両帝の感謝の念いが如何に大きかったが判る事実である。
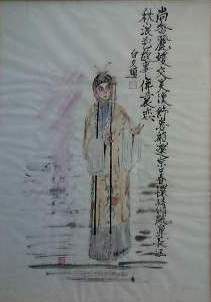
天智、鎌足の復古政権と近江遷都に見られる様な逃避外交に対して、国内の意見を一つに纏めて強力な中央集権国家を建てて唐新羅軍の来襲に備えようとした蘇我政権の積極外交政策を復活させなければ、日本は百済の様に滅ぼされてしまうと考える集団、開明的な豪族が明日香の地にいた。其の集団が頭目として担いだのが近江の都を逃れて吉野に隠っていた大海人皇子(後の天武天皇)で在った。
「大化の改新」に対する従来の誤った見方、”蘇我一族による天皇家を無視した政権を打ち破って天皇家が政権を取り返し、中央集権国家が築かれた”という学説に筆者は異を唱える”事は前頁に記した。
聖徳太子の政策を継承した蘇我政権の理想が、中大兄皇子や鎌足等のクーデターによって足踏みを余儀なくされた。白村江の戦いに敗れ、壬申の乱を経て再び、大王家の周りに開明豪族が集まって中央集権国家建設という聖徳太子の夢の実現に向かって歴史は歩み始めたのである。
壬申の乱にイニシアチブを執って大海人皇子に勝利をもたらせたのは海人族である。”吉野に逼塞していた大海人皇子が海人族を頼って吉野から明日香、伊賀を経て当地に逃れて来たのには訳がある”と前桑名市博物館長の大塚由良美女史(筆者が女史から個人講義をお聴かせ頂いた時は桑名市の生涯学習課長を為さっておいででで在った)は語られる。つまり、大海人皇子の食邑(領地)が此の周辺に在ったと仰る。大海人皇子の海人という文字は海人族の支配地に食邑が在った所から採られたか、海人族と何らかの深い関係が在った事を表す。筆者も此の説に賛成である。
大塚女史は更に、"大海人皇子は、此の地に到着した其の日の内に高市皇子や舎人を従えて「不破の関」に攻め入った”と説かれる。即日の挙兵、一ヶ月間の制圧は時間的に早過ぎる。逃げ込んで来た人間に一族の運命を託す事は大きな躊躇がある筈である。事前の根回しが完全でなければ実現しない。恐らく、大海人皇子が吉野に逼塞している間に、挙兵の根回しが終わっていた。”身一つをもって行けば好い状況に在った”と語られる。
斯くして大海人皇子と海人族は約一ヶ月の戦いを経て政権を奪い取り、都を明日香の旧都に戻すのである。「壬申の乱」には正妻の鸕野讃良{後の持統天皇}や幼い息子達、大津皇子や草壁皇子達は従軍をしていない。当地の豪族の庇護下に置かれた。
大塚女史は続ける。"妻や子供を預ける程、大海人皇子と海人族の間に信頼があった”と。其れも頷ける。しかし、海人族側からすると人質で在ったかも知れない。もし、挙兵が成功しなかった場合、妃の鸕野讃良と息子達による第二戦線の構築という大海人皇子と海人族の長の布石で在ったかも知れない。何れにせよ、海人族と大海人皇子の間に深い信頼があったことは想像出来るので在る。
”壬申の乱”ー海部族と大海人皇子ー