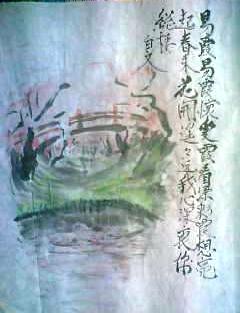
聖徳太子によって始められた中国大陸からの文化移入つまり、"中国に列ぶ文化国家を建設しよう”という夢は、遣隋使の派遣から約一世紀半余りの短期間で、もたらされた文籍を咀嚼消化して自分のものにし、其の得た知識を更に、発展させて中国に送り返し、中国の知識人を驚かせる迄に成長するので在る。
宝亀三年(公元七七二年)の遣唐使節の一員、僧戒明によって揚州の竜興寺の僧霊裕に献呈された、聖徳太子が撰した仏典注釈書の「三経義疏」の内「法華経義疏」と「勝鬘経義疏」を看た揚州の法雲寺の僧侶明空が「勝鬘経義疏」の漢訳注釈書「勝鬘経義疏私鈔」を著す。
此の様に、聖徳太子の仏典研究は大陸の学識僧をも驚かせ、逆に仏典を輸出した仏僧達にも知識を及ぼすので在る。また聖徳太子の著作のみ為らず、当時の日本人文人達の学識は唐の文人達に驚異を与え、唐朝廷内でも日本人が重用され、高位の官僚に抜擢されるまでに為るので在る。
休日の午後
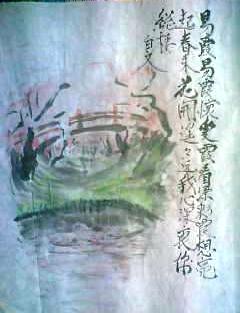
「屁放き爺さん昔~しのお噺」
593年:聖徳太子推古天皇の摂政と為り、改革が始まる。此の前年:推古天皇即位。
600年:第一回遣唐使派遣
602年:冠位十二階制定。翌公元603年十七条の憲法。
606年:聖徳太子、推古天皇等に「法華経」、「勝鬘経」を購読。
608年:第二回遣隋使派遣。小野妹子裵世清と帰国。翌609年:「勝鬘経義疏」一巻完成。
610年:遣隋使再び派遣。多くの留学生僧(高向玄理、僧旻、南淵請安等)を派遣。
611年:「維摩経義疏」三巻完成。
613年:「法華経義疏」四巻完成・
614年:遣隋使派遣(四回目)。
618年:隋王朝滅亡、唐王朝建国。
620年:「国記」、「大王記」、「臣連伴造国造百八十并公民等本記」を撰録。
622年:聖徳太子没、於斑鳩宮。
628年:蘇我馬子没
628年:推古天皇没。翌629年舒明天皇即位。
630年:第一回遣唐使派遣。
641年:皇極女帝即位。
643年:聖徳太子の長子、山背大兄王一族蘇我入鹿によって滅亡。
645年:「乙巳の変」(大化の改新)によって聖徳太子、蘇我氏の改革政治頓挫。
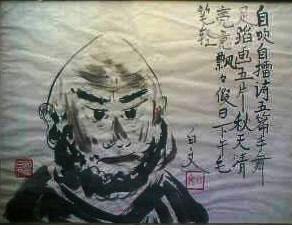
巻三の3
”文籍輸入と聖徳太子の夢”第1篇
聖徳太子が国家統治の基とした「法華経」、「勝鬘経」、「維摩経」の三つの経文の注釈書つまり、「三経義疏」に付いて少し、詳しく述べる。
隋王朝による南北統一に先立つ南北朝時代、南朝の一国家、梁王朝の創始者蕭衍(高祖武帝)も菩薩天子と讃えられ、仏教が保護されて多くの経典が研究された。因みに周興嗣によって「千字文」が書かれた。此の「千字文」は其れまで文字を持たなかった我が国に大きな影響を与え、後の「万葉仮名」、草書を更に展開させた「かな文字」を創り出し、女性の知識向上を足して「源氏物語」等の平安時代の女性文学に到るのは後の事。
聖徳太子著「三経義疏」の内、「法華義疏」は梁代の僧法雲(476年 - 529年)によって書かれた注釈書「法華義記」を元に書かれ、「勝鬘経義疏」は敦煌莫高窟に出土した「勝鬘経義疏本義」と未発見の6世紀前半と推定される注釈書をもとに、「維摩経義疏」は同じ梁代の僧吉蔵(549年-623年)の「維摩経義疏」や敦煌出土の「維摩経義記」と類似している事が報告され、天竺僧の僧肇(384年 - 414年?)の「註維摩詰経」や智蔵(458年 - 522年)の説を論じたものと云われる。
中国に「三経義疏」の元が見付けられると云う事は・・・・。聖徳太子が遣隋使派遣の際に命じた”国家に経典は多からず。よって小野因高を派遣して書籍を購わ使む・・・”に従って、購入帰還した多くの書籍から此の三経と其の注釈書を選び出し、自ら我が国の推古女帝や蘇我馬子らの重臣、冠位十二階によって登用された官僚達に講読教授し、読ませ、学習させて「十七条の憲法」、仏教思想に基づく国家建設と統治を行おうとしたと筆者は思うのである。
聖徳太子著「三経義疏」に絡んで
ー仏教の教えに基づく国造りー
淡海三船著の「大乗起信論注」や三船と共に「文人の首」とされた石上宅嗣が著した「三蔵賛頌」を読んだ唐の内道場{唐王朝の宮廷内の仏道修行所}の大徳飛錫{大徳:庁の長官}等は宅嗣の学識と文才に大いに驚いたと伝えられる。因みに、淡海三船は又、思託から資料の提供を受けて鑑真和上の東下の子細を記した「唐大和上東征伝」を撰集したと云われる。
此の様に聖徳太子の日本を改革して大陸の世界帝国の様な文明国家を築こうと云う夢は、一世紀半後の天平時代に建てられた「平城京」と為って花を咲かせるのである。
此処で聖徳太子の活躍と挫折を年表に表示すると、下記の表となる・・・・・・・。
「三経義疏」(さんぎょうぎしょ)とは聖徳太子によって著されたとされる「法華経」、「勝鬘経」、「維摩経」三巻の経文のそれぞれの注釈書、「法華義疏」四巻、「勝鬘経義疏」一巻、「維摩経義疏」三韓を指す。
日本書紀に推古天皇14年(公元606年)欄の記載に”聖徳太子が勝鬘経と法華経を講じた”と記されている。法隆寺等に残る古書から「三経義疏」は聖徳太子の著したものと信じられてきた。其の内、「法華義疏」のみ聖徳太子真筆の草稿とされるものが宮中に残存しているが、「勝鬘経義疏」、「維摩経義疏」は後の時代の写本が伝えられている。