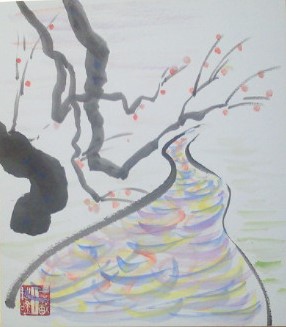天満宮を辞して上七軒の花街を散歩する。朝だった事も在って通りや置屋、茶屋はすだれが下げられ、靜もる。昼食や食事も手軽に提供されるお店も在って、花街の雰囲気を味わえる様で在る。北野おどりの宣伝看板が貼られている。此の花街は北野天満宮建設の余材を利用して茶屋が七軒建てられたのが始まりという。京都の五つの花街の筆頭でも在る。夜に為ると、芸妓や舞妓さん方が装いも艶やかに御茶屋に向かい、其れを見ようと観光客や酔客で通りは「賑わうんだろうなあ」と・・・。しかし、今はシーンとして芸妓や舞妓の気配も酔客のざわめきも全く、感じられない。
上七軒 花街の朝は 人も疎ら 夜の賑わひ 忘れたる如く
上七軒の筋違いの千本釈迦堂に参拝する。有名な年末のお釈迦様の大根煮回向の賑わい、今何処??本堂前の阿亀桜と呼ばれる枝垂れ桜は未だ、蕾を固くして咲く気配も見せない。千本釈迦堂は鎌倉時代中期、貞久三年(1221年)に藤原秀衡の孫義空上人によって、釈迦如来立像を本尊として創建された。其の御堂は洛中、最古の建造物で在るが、応仁の乱でも奇跡的に焼失することなく創建時の姿を今も、聳えさせている。しかし、其の御堂には哀しい故事が語られる。其の故事とは・・・・。
御堂の建立時、棟梁の長井高次は本堂を支える親柱の四本の内の一本を短く切り落とした。 悩み嘆く棟梁に妻の阿亀は「残りの柱を短く切り揃え、桝組を入れて高さを合わせれば好い」と進言して無事、御堂は完成した。阿亀は「女の知恵を
借りて完成させたと在っては主人の恥」と自害したと云う。彼女の功績忘れまいと枝垂れ桜が植えられた。「阿亀桜」と云う枝垂れ桜は今も、花を咲かせて阿亀の哀しい故事を伝えるので在る。 平成29年3月12日(日、晴)
釈迦堂の 故事も哀しき 阿亀桜 蕾堅けれ 弥生始まる
早朝、地下鉄とバスを乗り継いで北野天満宮に梅の香りを看に行く。紅白梅の花の香りが漂い、Spring has already comeと言っている様で在る。北野天満宮の奥に秀吉が築いたお土居が「古の都の境界は此処だよ」と言うが如く、今も聳えている。
参道に東向観音寺が建つ。寺の奥庭には道真の母公の墓所、「伴氏廟」と呼ばれる石柱が聳え、傍らの「土蜘蛛塚」が滅ぼされた者の哀感を漂わせて佇む。伴氏とは名門豪族大伴氏の事で在る。貞観年間に応天門の炎上事件に絡んで藤原良房によって伴善男、中庸父子は遠流に処され、名門大伴氏は滅亡に追い込まれた。石碑の「伴氏」とは菅原道真の母公を指す。
藤原時平によって太宰府に左遷され、恨みを抱いた儘、太宰府で亡くなった道真の怨霊ほど暴れた悪霊は古来、無い。道真の怨霊天神様は疫病を流行らせ、飢饉を招き、雷に変身しては大極殿を焼く・・・・・。藤原氏は勿論、人々のみか遂には、帝をも恐怖に陥れ、戦慄させた。道真の怨霊は、自身の恨みも有ったろうが、冤罪で滅ぼされた母公の出身一族、大伴氏の恨みもあったで在ろう。其処で朝廷は道真の名誉を回復し、北野の地に社殿を建てて其の霊を祀った。此が北野天満宮で在る。
参道に東向観音寺を建てたのも、道真の母公の大伴氏を祀って恨みも和らげようとしたのではないかと筆者は想像する。伴氏廟の傍らには土蜘蛛の石墓が列ぶ。土蜘蛛とは古、大和朝廷の列島征服に抵抗した多くの種族の総称で在ろうか??源頼光(朝廷派遣軍)に征服されたとされる土蜘蛛一族が、此の寺院の観音様の傍らに祀られている事も、哀感を感じさせる。
伴氏廟も 土蜘蛛塚も 観音の 掌に眠りて 訪ふ人も無く
天満宮の 賑わいよそに 参道に 忘らるるがに 観音佇む
「求古尋論 散慮逍遥」
「都の辰巳に棲まいして・・・・」第一編
語尾を伸ばしてトーンを上げるのは柔らかい雰囲気を醸すので気に入っています。「・・・ですー」の「ですー」の部分が上がって、伸ばされます。博士のお母さんも語尾を上げて、伸ばされて話されたんでしょうか???」。
博士から貰った返信メール
「京都の女性の「です」、「ですえ」の語尾変化はその時の気分によって変わり、きつく言う場合と普通に、好意を持っていう場合とで異なったと思います。貴志さんの感じたものはどちらかというと好意的な場面で使われたものと思われます。軟らかい雰囲気になるように意識して使われている様です。姉なんかも他人にはそんな話し方をしていた様な気がします。母の場合はそれが「どす」、「どすえ」になります」と。
清水寺十一面観音様の三筋の小水
夕方、地下鉄とバスを乗り継いで、清水寺の夜間参拝に行く。長い清水道を上って更に、石段を上る。京都の夜の灯りが瞬く。宛ら「雑華厳浄 青黄赤白」という華厳を表わした句は、斯くの視景を詠ったのかも知れない。音羽の滝の水を吞んだ。「音羽の滝」というが三本の長く突きだした筒樋の先から流れ出す水を、此も長い鉄柄杓を伸ばして汲み、手水を使い或いは、吞む。三本の樋から清水の流れ落ちる様はまるで、三人列んだ男がオシッコを垂らし飛ばす如き様で在る。清水の観音様には甚だ、失礼な言い方で在るが音羽の滝水も随分と、黄色く泡だったもの在る。否、十一面観音様、陳謝!陳謝!
清水の 音羽の滝は さながらに 小水三本 垂れ落ちる如く
観音に 手合わせ真摯に 祈る妻 清水舞台に 都の灯瞬く
清水坂の大日如来座像
清水坂に祀られる大日如来座像は、東日本大災害の大津波にも流されず残った陸前高田の一本松から彫り出された仏様で在るとか。丁度、今日はあの大津波から6年目で在る。沢山の参拝客にも拘わらず、手を合わせる若者が少ないのが寂しい。
大日如来 津波を耐へたる 松彫りて 現れし御姿 清水道に坐す
清水道の下り坂を右に折れ、三年坂と二年坂を経て石塀通りの灯りを鑑賞して、祇園石段下からバスに乗って帰る。敬老パスが我が都巡りに大いに力を発揮して呉れる。有り難い事で在る。 平成29年3月11日(土、晴)
二年坂 産寧坂に 石塀路 列びし灯に 十三夜の月
春宵一刻東山花灯路の花飾り
「東山花灯路」と名付けられた万灯会に行った。八坂の塔法観寺の手前の八坂庚申堂に茅の輪が置かれて在る。本来、茅の輪潜りは「水無月祓え」と云って6月末の筈で在るがまあ、好かろうと茅の輪を潜って庚申様に厄を払って貰った。好い加減なもので在る。 さて愈、東山花灯路散歩の開始で在る。八坂の塔から高台寺、円山公園、知恩院を経て青蓮院の間、道路の両脇に灯籠が列び、所々に生け花が飾られて華やいだ春の気分を昂揚させる。また、着物姿の美女が沢山、歩行しているのも華やかな雰囲気を醸す。
女房殿は石塀小路がいたく、気に入った様子。確かにムードのある小径である。ねねさんが晩年を過ごした圓徳寺が石塀小路から東山メイン通りに出た処、門内を夜間照明されて高台寺に対している。子供達の行列が京の通りの名を唄った童歌「丸竹恵比寿に押御池・・・」と歌いながら通り過ぎる。花灯路のイベントの「狐の嫁入り」のお狐さまの白無垢姿が人力車に乗って進んで来た。・・・・。 しかし、我々老夫婦もほんまに、好く出歩く。困ったものである。 平成29年3月5日(日、晴)
花灯路 灯りの彩り 処々の花 和装の娘等 路地の春宵
小林博士へ、京女の会話に付いて質問メール
「此方に来て一つ奇異に思ったこと。其れは、此方の女性が話す時に語尾のトーンを少し、上げて伸ばします。これは、京都の方言??の為せるワザでしょうか??
ー瓢逸白文京都はんなり歌草子ー{第三輯、桜咲く}
春は曙、川原の畔
「SPRING HAS COME」 (春が来た)」巻二