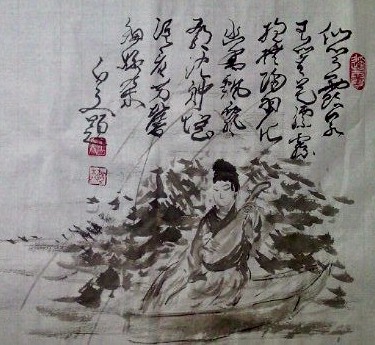
新羅によって国を追われた半島南岸の(倭国の一国、任那??狗邪韓国の後継国)の人々は、有力な指導者に率いられて朝鮮海峡を渡って倭国の地に逃げ帰った。 一説によれば、金官伽耶の仇衡(クヒョン)王が此のリーダーで在り或いは、仇衡王は欽明天皇だ”とも云う。筆者は此の半島南部から日本へ南遷した人々の指導者は継体天皇つまり、日本書紀の云う男大迹王では無かったか??と想像する。しかし倭国は既に、多くの国家がそれぞれの地域温暖な、瀬戸内海に面した地域を治めていた。其処で彼等は、日本海沿いに北上せざるを得無かった。出雲の国を滅ぼし、越の国に到る。此が出雲神話つまり、大国主命の国譲りと、国引きのお話であるかも知れない。
其の後、人々から大王に推挙された継体天皇(男大迹王)による越の国や近江、山背を従えて大和に進出して此処に支配国家を建設する。
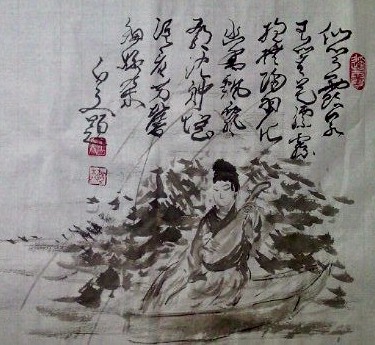
「屁放き爺さん昔~しのお噺」
寝物語第四
「斯くして日本は生まれた」
継体王朝(大和政権)と難波政権の倭国の支配を繞る戦い。大和政権の勝利、欽明王朝の始まりへと歴史は展開したと想像するのである。
大和政権と難波政権の戦いの中で、蘇我物部戦争が生じ、様々の葛藤を経て徐々に大和政権が日本列島の支配を伸ばす。前方後円墳という卑弥呼の祀祭に始まった倭国の墓陵が、倭国の東遷によって難波の地に大規模に造営され更に、前方後円墳文化を受け継いだ大和政権によって、日本列島各地に前方後円墳という墓陵文化が広まったと想像するので在る。
奈良には越の国に繋がる物語が多い。越前から鷲に掠われた良弁僧正や若狭国との結び付きを今に伝える「若狭井の水」{東大寺修二会のお水汲み}などである。また、仏像や仏典を日本にもたらした百済では、仏教は差ほど普及せず朝鮮半島では寧ろ、高句麗や新羅に仏教は広まった。此も、難波の物部氏や中臣氏{西の漢に属する豪族}は旧来の信仰を守り、蘇我氏などの大和豪族{東の漢}が仏教に魅せられた事に顕れているかも知れない。また、朝鮮半島南部、百済や新羅に越の国、糸魚川産の翡翠から削り造られた勾玉が多く掘り出され、半島南部と越の国の結び付きが物語られる。
聖徳太子は高句麗僧慧慈から仏教を学び、四天王寺や法隆寺を建立し、三経義訴を講じたのも越前王朝の大和征服説更に、難波王朝併合説を証明するかも知れない。前にも述べたが、現天皇家の興りを欽明天皇或いは、継体王朝に結び付ける説も唱えられる。筆者は仇衡で無くても、任那滅亡時に倭の地に帰還した倭の一支族の王による大和地方での建国、浪速に巣喰った倭国の主流王朝との戦いを経て、大和国が日本列島の支配権を確立して前方後円墳文化が日本を席巻したと想像する。
斯くして日本は、”澪つくし浪速の都”から、”飛ぶ鳥の明日香の都”へ、聖徳太子という天才を得て”青丹よし平城の都”へと、大唐の都にも匹敵する爛熟期を迎えるのである。
公元414年に建立され、日本陸軍による改竄が疑われていたが、其の改竄が否定され、歴史的価値が再び認められた高句麗「広開土王碑文」や「三国史記」、「三国遺事」という朝鮮半島の史書を読むと、公元350年頃から500年頃の間、倭国勢力が半島を蹂躙し、百済や新羅を支配下に徴税を行い、高句麗へも侵入した事が知られる。此の倭国の勢力とは魏志倭人伝に記される「狗邪韓国」の後継国家「金官加耶」或いは「駕洛」、「任那」等と呼ばれ、半島南端に所在した国家で在ったという。
Once Upon A Time For Japan Birth巻四
公元532年に金官国(狗邪韓国の後継国)が新羅に滅ぼされ、倭人達の朝鮮半島南端の地は失われ、海経を越えて南下が始まった。
其れと同時期或いは、それ以前に北九州の倭人達の東遷が本格的に行われ、温暖で肥沃な瀬戸内海の沿岸から浪速にかけて多くの国家が建設された。北九州の倭人達の東遷の理由は分からない。卑弥呼が戦って敗れた狗奴国が再び北征を始め、東に逃走を開始したか?或いは、新天地を求めた邪馬台連合の一支隊、一国或いは多くの人々が東に船を出したか?は筆者には判らない。或いは、此の倭勢力の東遷が古事記や日本書紀に語られる神武東遷伝で在ったかも知れない。
何れにせよ未だ、此の時期は大和盆地は未開の地で在ったと想像する。
此の倭勢力の朝鮮半島に於ける活発な活動は、中国南朝各王朝に対する倭の五王の朝貢、冊封の時期と重なり、また、公元410年東晋王朝が南燕王朝を征服して山東半島が南朝の勢力下に入り、鮮卑族の建てた北朝北魏王朝の勢力が南進し始める迄の時期にも重なる。此の東晋の山東半島支配開始時期に向応する様に倭王の南朝各王朝に対する朝貢が始まり、北魏の南進時期には下火に為った事を知る。
中国南朝に朝貢をし、冊封を得た倭王達に与えられた称号は概ね、一様である。其れは「使侍説・都督、倭新羅百済任那秦韓慕韓六国諸軍事、安東大将軍」と在り、偶に”安東将軍倭王に叙す”と記される。此の叙位を見るに、「倭」は百済や新羅、任那と横並びに記される。此は「倭」王国は、中国の史書「旧唐書」や「新唐書」に、”倭は古の漢の倭の那国で在る”と述べられる様に九州北部に所在した邪馬台連合の後継国ではないかと想像出来るので在る。大和地方からでは朝鮮半島に攻め込むにも、中国の南朝に使節を送り、冊封を得るにも遠すぎる。また、半島南部の人々や国々との接触するにも離れ過ぎるのではないだろうか??
筆者は、”倭王は北九州の邪馬台連合国家群の一国の王で在る”と思う。他に、”加羅や加耶等の狗邪韓国の後継国つまり、半島南部の倭人国の王が南朝各王朝に朝貢をして「倭王」という冊封を求めて許された”と云う可能性も仮説の一つに加えて今後の研究課題にしたいと思うので在る。
八世紀に書かれた「日本書紀」には此の時期、任那には日本府が置かれていたという。”「任那日本府」とは戦前、戦中の「朝鮮総督府」の様なものが想像されるが、実態は半島南部の倭人達{魏志倭人伝に書かれた狗邪韓国の子孫}の政治軍事集団??或いは、加耶諸国と其の周辺に残った倭人の集団で在ろう”と想像するのである。
更に大胆な想像を付け加えさせて頂きたい。
続「朝鮮半島と倭国の関わり」
